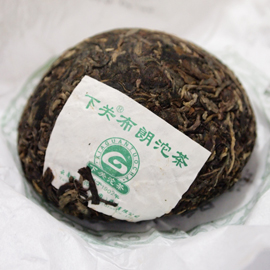4月の中国出張では発送業務をお休みさせていただき、みなさまにはご不便、ご迷惑をおかけしました。
今回は緑茶の新茶を中心に選んできました。
日本人は新茶に対して特別な思いを持っています。本来は中国茶も日本茶も、できたての新茶ではなく、少し時間をおいて落ちつかせたお茶のほうが味わい深いのですが、やはり春の訪れを知らせる新茶は特別です。これは中国の人々にも同じような感覚があるようで、日本ほどではありませんが、お茶市場ではいつもとは少し違う、なんとなく浮足だったような雰囲気に包まれていました。
今年は中国でのお茶の価格が下がったと言われています。政府が高額な接待や贈り物を禁止したため、一番の贈り物とされてきたお茶の需要が少なくなったからのようです。確かに春の新茶でいつもとは違う雰囲気の市場ではあるものの、例年よりも人出が少ないような感じでした。
では確かにお茶の価格が下がったのかというと、実際に価格が下がったお茶は普通には手が出ないような超高額のお茶に限定されていたようです。まさに贈り物とされてきたお茶が対象となっていたようで、それ以外のお茶は例年通りか、物価や人件費の上昇に合わせて値上がりしています。ちょっと残念ですが、市場価格とは関係なく、昨年の取引量が予想を超えるものであったおかげで、私たちが取引させていただいている作り手さんや茶業さんたちからは少し抑えた価格で提供していただくことができました。今年の緑茶は昨年よりも少しお求めやすい価格になっています。これもご利用いただいているみなさまのおかげです。どうもありがとうございます。
今年も鈴茶堂では四川の緑茶を選びました。
各地の作り手さんや茶業さんからから沢山のサンプルをいただき、様々な地域の緑茶を試飲してきましたが、やはり、昨年と同様に四川の作り手さんの作る緑茶が一番美味しく、他のお茶とは違う魅力がありました。
特に今年は蒙頂甘露の出来が素晴らしく、貢級と特級、2つ等級の蒙頂甘露をご紹介することにしました。どちらも素晴らしく美味しく、それぞれの個性が違うので選びきれませんでした。貢級は最高品質の蒙頂甘露です。とても小さな萌葉が白毫(シルバーチップ)に覆われていて、まるで銀粉のような美しい茶葉です。素晴らしい香りと繊細で上品な味わいで、初春を感じさせる緑茶になっています。特級はそれよりも少し成長した茶葉で作られ、繊細な貢級に対して、ふくよかで、キャラメルビスケットのような香りと甘味を持つ日本人好みのお茶に仕上がっています。
2013年 貢級 明前 蒙頂甘露
2013年 特級 明前 蒙頂甘露
蒙頂石花は伝統的な製法で作られたタイプに変わりました。四川では蒙頂甘露よりも好まれているお茶で、昨年ご紹介したものは伝統的な製法を更に改良した作り方で製茶されたタイプでした。今年は伝統的な製法で作られたタイプをご紹介します。また違った美味しさをお楽しみいただけると思います。あまり日本では知名度のないお茶ですが、味わいは名前の知られている蒙頂甘露よりも日本人好みです。今年の蒙頂石花は甘味に加えて、塩気を感じるような上質な美味しさがあります。
もう1つ、雲南の緑茶も選びました。
雲南省南部にある思茅地域で作られた早春茶です。今年最初に摘み取られた茶葉から作られている緑茶です。
雲南緑茶というと柑橘系の果物の香りのあるものが多いのですが、この早春茶は甘い桜餅のような香りがあります。それだけでなく、雲南紅茶を連想させるような甘い味わいがとても美味しく、これは是非ご紹介させていただきたいと思い、入荷することにしました。
新茶は緑茶だけではありません。
人気の高い四川高山紅茶の姉妹版とも言える四川玖瑰紅茶も入荷しました。
通常の四川高山紅茶は今頃から初夏にかけて作られますが、これは緑茶と同じような早春に摘み取られた繊細な茶葉を使用して作られた紅茶です。「玖瑰(メイグイ)」と名前にあるのはバラのような香りがあるからです。
一般的に言われる「玖瑰紅茶」は後からバラの香りを添加したり、花茶のように花の香りを移した紅茶ですが、この紅茶は違います。茶葉本来の香りがまるで可憐なバラのような、甘い繊細な紅茶です。
他にも珍しい黄茶、蒙頂黄芽も入荷しています。
黄茶は皇帝献上茶として珍重されてきましたが、生産数が少なく、今ではなかなか見つけられない貴重なお茶です。独特の風味をもつものが多く、好みが大きく分かれるお茶でもあるのですが、この蒙頂黄芽は誰もが美味しいと思うような品格のある黄茶に仕上がっています。
この蒙頂黄芽を作っている作り手さんはとても真摯で真面目な方で、農閑期には大学で製茶について教鞭を取っています。その作り手さんが蒙頂黄芽をより美味しくするために研究して作りだしたお茶です。伝統的な製法を守りながらも技術を少しずつ改善していった集大成ともいえるこの蒙頂黄芽は、私たちが知っているどの黄茶よりも遥かに美味しいお茶になっていました。
これらのお茶が作られた四川省雅安市では4月19日、大地震が発生、大きな被害が出ております。
私たちとお付き合いのある蒙頂山および雅安の作り手さん、茶業さんたちには幸いなところ、軽傷はあったものの、大きな人的被害はありませんでした。しかしながら、被害の大きい地域と近い地域のため、揺れが激しく、建物の一部倒壊などがあったそうです。今も余震が続く中、懸命に復旧作業に努めています。
当店でご紹介する四川茶は全て震災前に製茶、輸入されたものです。
今年の新茶はどれも捨てがたい位に美味しいお茶ばかりです。それだけに四川雅安地震は本当に辛く、毎日ニュースを見ては心が締め付けられるような思いでいます。幸い、私たちの友人や知人に人的被害はなかったものの、何度か訪れているこの雅安とその周辺では日本人だということで、前回の四川大地震での日本の支援に対してお礼を伝えてもらったり、東日本大震災を心配していただいたりと、とても良くしていただきました。素朴で優しく、素敵な地域です。
被害が最も酷いと伝えられる地域は、平常時でも細い山道に落石や崩落が頻発しているようなところで、地図ではほんの2時間程度の場所でも実際に移動してみたら5時間もかかるような場所です。救助や支援活動が難航しているようですが、安否が分からない方々がどうかご無事でありますように、そして被災された皆様が早く安心出来るよう、祈らずにいられません。そして亡くなられた方々に心よりお悔やみ申し上げます。
出来ることから、何かお手伝いができたらと思っています。
鈴茶堂では当面の間、蔵茶、蒙頂茶などの四川のお茶の売上の一部を義捐金または支援物資に変えて送らせていただきます。